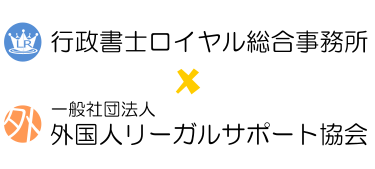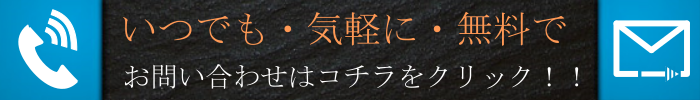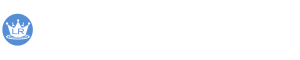このページの目次
平成28年に国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業が始まり、日本の家事代行業者様が外国人を雇い入れることが可能になりました。
平成28年11月時点では現時点では大阪で2業者、神奈川で4業者が外国人家政婦を受け入れ始めています。ある事業者では一度に25名の外国人家政婦を受け入れたようです。
本記事では、これから外国人家政婦の受け入れを検討している事業者様向けに、①【外国人家事支援事業を始めるべきか否かの判断材料】と、②【外国人家事支援事業を始めるまでの手続き】について解説します。
外国人家事支援事業を始めるべきか否かの判断材料
まずは外国人家政婦を受け入れるべきかどうか、外国人家事代行・家事支援事業を開始すべきかどうかを検討しましょう。
外国人家政婦の魅力
まず外国の家政婦は非常に良質であり、家事業務ついて技術力に長けております。
特にフィリピン人による家事能力は非常に質が高いと世界でも認識されており、フィリピンは国を挙げて家事支援人材として自国民を様々な国へ送り出しています。
外国人家政婦が出来る事・出来ない事
国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業により、家事代行事業者が外国人家政婦を雇い入れたとしても、日本人家政婦と同様になんでも出来るわけではありません。
法令によって、外国人家政婦の業務内容が制限されています。
外国人家政婦が出来る事
国家戦略特区家事支援事業で受け入れた外国人家政婦が出来る事は下記のとおりです。
- 主業務
-
- 炊事
- 洗濯
- 掃除
- 買物
- 付随業務
-
- 子供の世話・送迎
- 要介護者の補助(介護活動を除く)
- その他、裁縫、荷造り、郵便・宅配等荷物受取、寝具の整備、庭の手入れ
付随業務はあくまでも主業務の付随的に行われるものでなければなりません。従って、主業務をせず付随業務のみをするという事は認められません。
要介護者の補助については、室内移動・外出・着替えの補助は認められますが、入浴・トイレ・食事補助等の介護活動は認められません。(配膳は認められます。)
外国人家政婦が出来ない事
家事労働活動の内容として出来ない事は、前述した通り、入浴・トイレ・食事補助等の介護活動は認められません。
それ以外にも下記のような事が禁止されています。
- 外国人家政婦を利用者の家に住み込ませてはいけない
- 外国人家政婦を事業実施区域以外の区域に派遣してはいけない。
- 利用者の指揮命令下で外国人家政婦を労働させてはならない。
- 短時間労働の禁止
事業実施区域は、現在のところ「大阪市全域」または「神奈川県全域」に限定されます。また、事業者の本社または直営事業所の所在地が「事業実施区域内又はこれに隣接する市町村の区域内」である必要があります。
短時間労働の禁止とは、家事代行事業者は外国人家政婦をフルタイムで直接雇用しなければなりません。労働日数が週5日以上かつ年217日以上かつ週30時間以上である必要があります。(利用世帯との間の移動時間を含む。)
外国人家事支援事業をする場合の事業者の負担
家事代行事業者が日本人家政婦を雇う場合は、求人広告で人材を募集し単純に雇い入れる事でしょう。
その点、外国人家政婦を雇い入れる場合は求人広告は不要なので、その分の広告費は削減できます。ある家事代行事業者は一度に25名の外国人家政婦を受け入れましたが、25名もの日本人家政婦を雇い入れる為の広告費は決して小さいものではありません。
一方で、外国人家政婦を受け入れる為には様々な負担も必要です。外国人家事支援事業の開始を検討している事業者にとっては理解しておきたいところだと思います。
- 外国人家政婦となる人材の発掘・選定
- 事業者が外国人家事支援事業者となる為の申請手続き
- 外国人家政婦の給料については、日本人が従事する場合の報酬と同等額
- 外国人家政婦の来日後の住居を確保しなければならない。(家賃は外国人負担)
- 受け入れた外国人家政婦に対し、必要な研修を行わなければならない
- 外国人家政婦の受け入れ後は、1ヵ月毎、3ヵ月毎の行政報告義務が発生
- 外国人家政婦の受け入れ後は、1年毎に行政からの監査を受ける義務が発生
3.の給料について、日本人と同等とは、事業者が雇用する他の日本人家政婦であってフルタイムで直接雇用する方と比較してください。同等額以上であればOKです。
その他の項目については次節の「外国人家政婦を受け入れる為に必要な手続き」で解説します。
外国人家政婦を受け入れる為に必要な手続き
外国人家政婦を受け入れるメリット・デメリットを検討し、受け入れたいと判断できれば、外国人家政婦を受け入れる為に必要な手続きを理解しましょう。必要な手続きは、時系列順に下記のとおりです。
- 受け入れる外国人家政婦となる人材の発掘・選定
- 外国人家事支援事業を行うための「特定機関」になる
- 雇用する外国人家政婦を来日させるためにするビザ申請
- 外国人家政婦が来日した後の管理・運営
本記事を読めば、流れがすべて理解できるように詳しく解説します。
受け入れる外国人家政婦となる人材の発掘・選定
(次項の【外国人家事支援事業を行うための「特定機関」になる】と並行して進めてください。)
海外で生活する外国人人材を募集し、現地で面接をして採用すればよいのですが、ほとんどの事業者がそのようなコネクションがないでしょう。
また外国人家政婦となる人材にも条件があるので(1年以上の家事支援の業務経験を有し、日本語能力N4以上)、そのような人材を家事代行事業者が見つけることは困難です。
従ってほとんどの場合は、海外人材の職業紹介事業者と連携して進めることになります。
当事務所でフィリピン人家政婦の人材紹介事業者を紹介させて頂きますので、要望があればご連絡ください。
外国人家事支援事業を行うための「特定機関」になる
(前項の【受け入れる外国人家政婦となる人材の発掘・選定】と並行して進めてください。)
事業者が外国人家政婦を受け入れる為には、外国人家事支援事業の「特定機関」として認定を受けなければなりません。
「特定機関」になる為の条件
「特定機関」になる為には、下記の条件に該当しなければなりません。
- 指針に照らして必要な措置を講じていること。
- 家事支援事業を遂行するための経済的基礎及びその他の能力が十分であること。
- 日本で3年以上、家事代行、または、家事代行の補助業務に係る事業を行っていること
- 欠格事由に該当しないこと
3.については「事業年数が3年」という明確な基準が示されています。これは主たる事業として営まれる必要はありません。また、事業統合等が行われた場合は統合前の会社の実績も含まれます。
1~2、4については次節で紹介する申請書に細かい内容が記載されていますので、そちらを見ていただいたらだいたいご理解いただけると思います。分かりにくい部分についてだけ解説します。
- 3-(1)-③⑥ 事業区域について
- 平成28年時点では、「大阪市全域」、または「神奈川県全域」に限定されています。外国人家政婦を派遣できるのはその2地域に限られます。そして事業者の本社または直営事業所の所在地は、事業実施区域内・隣接市町村になければなりません。
- 3-(1)-⑦ フルタイムとは
- 労働日数・労働時間が週30時間以上・週5日以上・年間217日以上をすべて満たさなければなりません。なお利用世帯との間の移動時間は含んでよいとされています。
- 3-(1)-⑮⑯ 必要な研修について
- 受け入れた外国人家政婦に対して、下記の研修を行わなければなりません。
-
- A.家事業務に関する教育訓練
- B.日本に在留する上で理解すべき関係法令に関する説明
- C.日本で就業する上で理解すべき関係法令に関する説明
- D.就労や生活に関する相談を受ける窓口に関する説明
- E.子育て支援員研修の中から関連する研修(子供の世話・送迎に関する業務を行わせる場合のみ)
- F.日本語コミュニケーション・非常時の対応に関する研修(他の研修で足りない場合で、かつ、必要な場合のみ)
- 上記は全て、事業者が研修を開催することもできますし、外部に委託することもできます。時間的にはAは20時間以上、BCDEFはそれぞれ数時間で完了するような内容です。
- 3-(1)-⑰ 相当数の労働者を非自発的に離職させているとは
- 過去3年以内に、1ヵ月の中で30人以上の非自発的離職者を発生させている場合を意味します。
- 3-(2) 「経済的基礎」「その他の能力」とは
- 「経済的基礎」とは、法人登記があり、過去3年分の売上・利益が健全であることを意味します(損益計算書、貸借対照表等の財務諸表で確認。)。「その他の能力」とは、外国人家政婦に対する仕事の指導・日本の生活について指導・その他相談に対応する体制を整えていることを意味します。
「特定機関」になる為の申請
申請書のダウンロード
まずは「特定機関」になる為の下記の申請書をダウンロードしましょう。
 様式第1号(特定機関確認申請書)
様式第1号(特定機関確認申請書) 様式第1号別紙1(役員名簿)
様式第1号別紙1(役員名簿) 様式第1号別紙2(外国人家事支援人材の受入れに関与する特定機関以外の機関)
様式第1号別紙2(外国人家事支援人材の受入れに関与する特定機関以外の機関) 様式第1号別紙3(出入国又は労働法令に関する不正又は著しく不当な行為)
様式第1号別紙3(出入国又は労働法令に関する不正又は著しく不当な行為)
添付書類の準備
- 業務方法書(事業計画書)
- 予定請負契約書
- 確保すべき住居に係る不動産賃貸借契約書(自社所有の場合は登記事項証明書)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)
- 予定雇用契約書
- 同等日本人報酬算定資料
- 研修計画書(家事支援活動に関する教育訓練)
- 研修計画書(在留上理解しておくべき法令)
- 研修計画書(就業上理解しておくべき関係法令)
- 研修計画書(苦情及び相談を受ける窓口)
- 研修計画書(5号業務を行う場合の研修)
- 苦情・相談窓口概要書
- 保護ルール概要書
- 就業規則
- 帰国費用負担の協定書(金融機関発行の保証書などでも可)
- 協議会設立趣意書(案)又は既に設立された協議会への加入予定書
- 過去3年分の財務諸表(B/S、P/L等)
- 業務指導体制図
- 生活指導・相談体制図
実際の申請
申請書・添付書類を準備し、正本(紙)1部と、PDF化したデータを保存したCDを2枚準備し、下記の提出先に持参します。(メール・FAX・郵送は不可です。)
- 提出先 : 大阪府第三者管理協議会事務局
- 受付場所: 大阪市経済戦略局立地推進部立地推進担当(特区担当)
- 所在地 : 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟 4階M-4
- 電話番号: 06-6615-3770
雇用する外国人家政婦を来日させるためにするビザ申請
日本の入国管理局で在留資格認定証明書交付申請
外国人家事支援事業を行うための「特定機関」の認証を受ければ、次は実際に外国人の方を来日させる為に必要なビザ申請に移ります。
ビザ申請は正式には「在留資格認定証明書交付申請」といい、大阪であれば大阪入国管理局へ申請しなければなりません。このビザ申請は複数名の外国人を受け入れる場合でも、各外国人に対して個別に申請する必要があります。
申請できる者は、外国人の方を受け入れようとする家事代行事業者の方が直接行ってもよいし、外部の行政書士等に依頼しても構いません。
申請書類は下記のとおりです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請前3か月以内のもので、裏面に記名してください。
- 返信用封筒
- 宛先を明記し、392円の切手を貼ってください。(簡易書留用)
- 特定機関基準適合通知書の写し
- 雇用契約書の写し
- 外国人の方の労働条件、従事する業務内容を明示されたもの
- 外国人の本国の人材育成機関が発行する証明書、雇用主が作成又は証明した在職証明書、履歴書
- 上記いずれかで、外国人が家事代行業務に関して1年以上の実務経験を有することを証明できる文書
- 外国人が家事支援業務を行う上で必要な知識と技能を有する事を証明する次の文書
- 出身国等の人材育成機関における研修修了証明書の写し
- (フィリピンの場合は下記3点が必要)
- 研修を修了した人材育成機関が発行する修了証明書
- 人材育成機関の研修を修了した旨のフィリピン労働雇用省技能教育技術開発庁(TESDA)が発行する証明書
- TESDA発行証明書が真正なものである旨のフィリピン外務省が発行する証明書
- 出身国政府による認定資格を有することの証明書の写し
- (フィリピンの場合は下記が必要)
- 「Household Services NCⅡ」または「Domestic Worker NCⅡ」のいずれかの資格を有することについて、TESDAが発行する証明書
- 出身国による国外就労のための許可証の写し又は当該許可証を取得した上で上陸申請する旨の特定機関が発行した誓約書
- 出身国等の人材育成機関における研修修了証明書の写し
- 下記いずれかの文書
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上の認定結果及び成績に関する証明書の写し
- 日本語能力特例特定機関の条件適合通知書の写し
在留資格認定証明書を海外の受け入れ外国人に送付
前節の日本におけるビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)は、1ヵ月~3ヵ月で結果が分かります。
入国管理局から在留資格認定証明書の交付を受けたら、その在留資格認定証明書を海外に居る受け入れ予定の外国人へ送付します。
受け入れ外国人が来日する際に、在留資格認定証明書を持参し、日本の空港で提出することになります。
外国人の本国におけるビザ申請
日本でのビザ申請とは別に、外国人の本国においてもビザ申請をしなければなりません。
このビザ申請は正式には査証申請といい、外国人の本国の日本大使館・日本領事館等で申請を行います。
申請からおよそ2週間で結果がわかります。在留資格認定証明書が既に交付されていれば、ほとんどの場合は本国におけるビザ申請も許可されます。(100%ではありません)
ビザ(査証)を受け取れば、日本に来日することができます。
外国人家政婦が来日した後の管理・運営
外国人家政婦が来日した後でも、事業者がしなければならない事がいくつかあります。
- 外国人家政婦に対する研修(業務に入る前)
- 外国人支援事業に関する行政報告(1ヵ月に1回)
- 外国人支援事業に関する行政報告(3ヵ月に1回)
- 外国人支援事業に関する行政監査を受ける(1年に1回)
これらについて後日公開します。