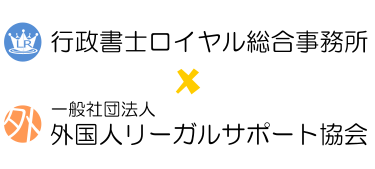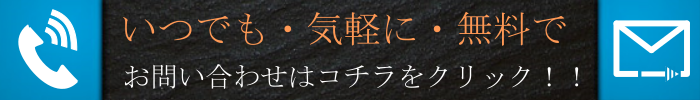このページの目次
本判決の意義は、退去強制事由に該当する売春行為をした場合でも、やむを得ない事情があって悪質性がない場合は、単に売春行為をした事のみを判断するのではなく、事情等を考慮すべきと判示した点です。
売春をした期間が短期間であること、自ら主体となって組織的に行ったものではないこと、娘の学費の為であることなどを理由に売春に悪質性はないと判断されました。
さらに、退去強制処分を受けた女性が日本人男性と実質的な夫婦関係が形成されていたこと、女性の母親が実は中国残留孤児であり日本国籍を有すべき者であったことなども理由として、判決の結果、退去強制処分が取り消されたものです。
裁判名
平成28年3月16日判決言渡 名古屋高等裁判所
平成27年(行コ)第32号 退去強制令書発付処分等取消請求控訴事件
(原審・名古屋地方裁判所平成26年(行ウ)第75号)
主 文
主文1
原判決主文第2項を次のとおり変更する。
(1) 名古屋入国管理局長が平成26年1月27日付けで控訴人に対してした出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を取り消す。
(2) 名古屋入国管理局主任審査官が平成26年1月27日付けで控訴人に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
主文2
訴訟費用は第1、2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者が求めた裁判
1 控訴人
主文同旨
2 被控訴人
(1) 本件控訴を棄却する。
(2) 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 事案の概要
概要1
本件は、中華人民共和国(以下「中国」という。)国籍を有する外国人である控訴人が、名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条4号ヌに定める退去強制事由(売春関係業務従事)に該当する旨の認定を受けた後、名古屋入管特別審理官から、上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため、入管法49条1項に基づき、法務大臣に対して異議の申出をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から、平成26年1月27日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受け、引き続き、名古屋入管主任審査官から、同日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため、本件裁決及び本件処分の各取消しを求めるとともに、本件裁決後に日本人男性と婚姻したことを理由として、名古屋入管局長に対して控訴人の在留を特別に許可することの義務付けを求めた(以下、この義務付けを求める訴えを「本件義務付けの訴え」という。)事案である。
原判決は、本件義務付けの訴えは不適法であるとして却下し、本件裁決及び本件処分の各取消請求については、控訴人は入管法24条4号ヌの退去強制事由に該当する外国人であると判断した上で、本件裁決に裁量権の範囲の逸脱又は濫用はなく適法であり、これを前提としてされた本件処分も適法であるとして、いずれも請求を棄却したところ、控訴人が控訴した。なお、控訴人は、当審において、本件義務付けの訴えの部分につき控訴を取り下げた(不服申立ての範囲の減縮と解される。)。
概要2
前提事実、争点及び争点に関する当事者の主張は、原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」2、3(1)、4(1)に記載のとおりであるから、これを引用する。
第3 当裁判所の判断
1 控訴人の退去強制事由該当性について
前提事実によれば、控訴人は、入管法24条4号ヌ(売春関係業務従事)の退去強制事由に該当する外国人であることが認められる。
2 認定事実
前提事実、証拠(甲10、11、24の1・2、25の1・2、26、当審における証人A、控訴人本人、掲記の証拠)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
(1) 控訴人の母親について
ア
控訴人の母親であるB(1939年(昭和14年)▲月▲日生。以下「控訴人母」という。)は、かねてから、自らが日本で生まれて中国へ渡った後中国の養父母に育てられたと話しており、昭和59年に当時の厚生省により行われた第1回訪中調査においても、昭和19年頃、父母及び兄弟姉妹とともに家族7人で東京から中国東北部(旧満州国)の哈爾浜(ハルピン)市へ渡ったこと、1945年(昭和20年)8月のいわゆるソ連参戦後、同市を逃れて奉天市(現在の瀋陽市)に移ったこと、同市で父と妹が亡くなり、母の依頼で中国人の養父母に引き取られた後、母、兄、姉及び弟と生き別れたこと、幼少の頃は「C」と呼ばれていたことなどを自らの記憶に基づき話しており、これらの調査を経て、当時の厚生省によりいわゆる中国残留孤児であると認定された。また、控訴人母は、昭和61年10月から11月にかけて当時の厚生省により実施された第13次訪日調査にも参加して来日したが、その身元が判明せず、「身元未判明孤児」とされた。(甲3の3ないし7(更なる枝番を含む。以下同様。)、甲9、27の1ないし5、28の1・2、29の1・2、乙1、12、22の1、当審における調査嘱託に対する厚生労働省社会・援護局援護企画課中国残留邦人等支援室長の回答)
イ
身元未判明孤児は、昭和60年3月29日付け厚生省援護局長通知(援発第208号)により、永住帰国援護の対象とされており、当該本人及び少なくともその未成年で未婚の子は帰国旅費国庫負担の対象となり(同通知の記1(4))、円滑に日本社会に溶け込んで自立し安定した日常生活が送れるよう、日本語や日本の生活習慣等を習得する研修、相談相手となる身元引受人のあっせん、職業の紹介等の支援を受け得る立場にあった。当時の厚生省は、昭和62年8月末頃、控訴人母を含む身元未判明孤児314名に対し、永住帰国希望調査票を送付し、控訴人母の下へも同年(1987年)9月頃にこれが到達しており、控訴人母は、様々な事情のために逡巡しながらも(甲3の4、甲3の5の1)、この頃には永住帰国の意思を固めていたが、同年10月▲日に病死したため、永住帰国には至らなかった。(甲3の3ないし7、甲9、27の1ないし5、28の1・2、前記調査嘱託に対する回答)
ウ
その後制定された「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年4月6日法律第30号)」は、中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの及びこれらの者を両親として同月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者等を「中国残留邦人等」と定義し(同法2条。以下、特に必要のない限り「中国残留邦人」と表記する。)、本邦への帰国を希望する中国残留邦人の円滑な帰国を促進し、帰国後の自立を支援するため(同法1条)の必要な施策として、永住帰国旅費の支給等(同法6条)や自立支度金の支給(同法7条)はもとより、生活相談等(同法8条)、住宅供給の促進(同法9条)、雇用や教育の機会の確保(同法10条、11条)等々の施策を講ずるものとしている。
エ
なお、国籍法附則(国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律[昭和59年5月25日法律第45号])5条1項は、昭和40年1月1日から施行日の前日(昭和59年12月31日)までに生まれた者で、その出生の時に母が日本国民であったものは、母が現に日本国民であり、又はその死亡の時に日本国民であったときは、施行日(昭和60年1月1日)から3年以内に法務大臣に届け出ることによって、日本国籍を取得できる旨を規定しており、同条3項は、上記3年以内に天災その他その責めに帰することができない事由により届出ができないときには、届出可能となった時から3か月以内と届出期間を伸長している。そして、現に平成18年から平成26年までの9年間に、国内外で合計133名(うち109名が中国籍の者)が上記5条1項に基づき日本国籍を取得しており、届出事由の多くが就籍(日本国籍を有していながら戸籍に記載されていない者につき、新たに戸籍を設けて戸籍に記載をすること)を理由とするものである(甲23)。
オ
また、中国残留邦人がその出生時にその父又は母が日本国籍を有していた場合等には、入管法別表第二の「日本人の配偶者等(日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者)」として在留資格が付与され、それ以外の中国残留邦人についても、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年5月24日法務省告示第132号)」(甲20。以下「定住者告示」という。)8号ニ「(ⅱ) 二十歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)」ないし「(ⅳ) 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(五十五歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの」に該当するものとして、入管法別表第二の「定住者(法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)」として在留資格が付与される。そして、本邦に永住帰国する中国残留邦人と本邦で生活を共にするために入国を認められる実子については、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年9月27日号外厚生省令第63号)」10条2号ないし4号により、前記の定住者告示8号ニ(ⅱ)ないし(ⅳ)に該当するものとして、入管法別表第二の「定住者(法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者)」として在留資格が付与され
る。なお、平成27年9月30日現在、永住帰国した中国残留邦人は6713人(家族を含めた総数2万0891人)であり、他方、一時帰国の延べ人数は5958人(家族を含めた総数9993人)である(甲21)。
(2) 控訴人の本邦入国までの生活状況等
ア
控訴人は、1968年(昭和43年)▲月▲日、中国の瀋陽市において、中国国籍を有する父親と、その妻であり、上記のとおり中国残留邦人である控訴人母の第1子として出生し、兄弟姉妹はいない。控訴人母は、1987年(昭和62年)10月▲日に死亡しており、同父は2005年(平成17年)9月▲日に死亡した。(甲3の4、甲9)
イ
控訴人は、1989年(平成元年)10月、当時勤務していた会社の同僚の中国人男性(以下「前々夫」という。)と婚姻し、前々夫との間に娘であるD(1993年(平成5年)▲月▲日生。以下「娘D」という。)をもうけ、1995年(平成7年)からは、遼寧省内の百貨店で販売員として働いていたが、前々夫とは2005年(平成17年)に離婚した(甲4、乙12、19、35)。
(3) 控訴人の本邦入国及び在留状況等
ア
控訴人は、かねてから控訴人母の母国である日本に対して強い憧れを抱くとともに、控訴人母の死亡後はいつかその遺骨(骨灰)を日本に持って行きたいと希望していたところ、インターネットで日本人男性のE(昭和35年▲月▲日生。以下「E」という。)と知り合い、平成21年6月▲日、中国国内において、Eと中国の方式により婚姻した。その後、控訴人は、Eと同居するため、同年11月26日に来日し、在留資格を「日本人の配偶者等」、在留期間を「1年」とする上陸許可を受けて本邦に上陸し、その後、Eとの同居を開始し、平成22年9月(平成23年11月まで1年間)と平成23年11月(平成26年11月まで3年間)の2回、在留期間の更新許可を受けている。(乙2、3、12、19)
イ
Eは、愛知県内に本社のある食品加工会社に勤務する会社員であり、控訴人は、当初はEとともに愛知県内に暮らし、その後、Eの転勤により千葉県に転居したが、Eとの夫婦関係はうまく行かず、また、東日本大震災により来日を見合わせていた娘Dを名古屋の学校に入学させる準備も考えて、平成23年11月18日、名古屋市a区内のマンションに単身で転居して、Eと別居するようになり、その後平成24年3月27日、同市b区内のマンション(現在の住所地)に転居し、来日した娘Dと暮らし始めた。Eは、別居後、上記マンションの賃料を負担した以外には、控訴人に対して経済的な援助をしなくなった。なお、控訴人は、平成21年11月の来日以来、平成22年6月、平成23年1月、同年3月、平成24年1月及び同年8月の5回にわたり、再入国許可を受けて本邦を出国して中国に短期間滞在している。(乙1、2、4、19、35)
ウ
控訴人は、平成24年12月29日午前1時頃、売春をする目的で、名古屋市a区内の路上を通行していた男性に対し、「1万5000円。最後まで。」などと申し向け、公衆の目に触れるような方法で人を売春の相手方となるように勧誘したというという売春防止法5条1号違反の罪(売春勧誘)により、平成25年1月▲日の逮捕及びその後の勾留を経て、同月▲日、名古屋簡易裁判所において罰金1万円に処する旨の略式命令を受けた(乙2、6、7、10、11)。なお、控訴人は、当時、Eから自宅賃料以外には生活費等の援助もない中で、娘Dの学費を稼がなくてはと焦って売春をするようになったものであるが、名古屋入管の入国警備官及び同入国審査官による取調べにおいて、平成24年9月から同年10月まで、名古屋市内にあるマッサージ店「F」で売春に従事して約40万円の収入を得、その後、同年11月頃、名古屋市内に自らが経営するマッサージ店「G」(以下「本件マッサージ店」という。)を開店し、同月から平成25年1月15日までの間、本件マッサージ店において不特定多数の男性を相手として売春に従事して約100万円の収入を得た旨供述している(乙10、11、19)。
エ
控訴人は、41歳で本邦に初めて入国するまで、中国で成育したため、母国語である北京語での会話や読み書きに不自由はなく、他方、日本語については、文字を読み、日常会話をすることができるほか、現在では日本語で相当程度の文章を書くこともできるようになっている(甲24の2、25の2(いずれも日本語による自筆の陳述書)、乙1、10、19)。
(4) 控訴人とAとの関係等
ア
控訴人は、平成23年11月頃、日本人男性であるA(昭和50年▲月▲日生。以下「A」という。)と知り合い、Eとの婚姻期間中ではあったが、同年末頃からAと交際を始め、平成24年3月頃にはAと肉体関係を持つようになった。Aは、調理師の免許を有し、高校卒業後大手のレストランチェーン「H」に約12年間勤務するなどした後、約6年前から現在の勤務先である名古屋市a区cの居酒屋「I」に勤務し、同店の料理長を任されて深夜零時から朝9時まで週6日働いている者であるが、現在は「主任」に昇任し、今後増設される店舗をも任させる予定である。控訴人は、上記「I」の客としてAと知り合ったものであった。(甲1、乙12ないし15、19)
イ
Aは、平成24年3月頃、控訴人が賃借したマンションの連帯保証人となり、控訴人とAは、婚姻することを前提として、娘Dが中国へ帰国した後の平成25年5月1日、控訴人の上記マンションに転居する形で同居を開始し、現在まで同所で一緒に暮らしている。控訴人とEは、同年8月▲日に協議離婚し、控訴人とAは、控訴人のいわゆる再婚禁止期間(待婚期間)経過直後である平成26年2月▲日、婚姻の届出をした。(甲1、4、乙2、5、13、22の2)
ウ
控訴人とAは、同居を開始した平成25年5月以降に認められる内縁期間中も婚姻期間中も、実質的な夫婦として仲良く暮らしており、その詳細は明らかでないものの、控訴人が一時期Aに秘してインターネットで化粧品の通信販売を行っていたことはあるが、その後やめており、夫婦の生活費は、Aの給与収入により賄われている(乙12ないし15、19)。Aは、控訴人が同年8月15日に名古屋入管へ出頭した際に付き添い、控訴人が名古屋入管に収容中であった同年11月27日から同年12月24日まで及び平成26年1月27日から同年8月25日までの合計約8か月間、仕事明けの午前中、連日のように名古屋入管へ通い詰めて控訴人に面会し(合計144回)、控訴人を精神面で支えようと懸命に努めていた(乙38)。当審において、Aは証人として出廷し、これまで控訴人と夫婦として一緒に過ごしてきているが、控訴人との事情を知る店のオーナーからも信頼されて仕事を任されており、地元には体調が良くない母親もいることから、今後も日本において控訴人との婚姻生活を維持していきたい旨供述しており、控訴人本人も、Aと一生涯寄り添って日本で生活していきたい旨供述しているところである。
(5) 控訴人の親族(娘D)の状況等
娘Dは、平成24年3月に来日して控訴人と一緒に暮らし、名古屋市内にある日本語学校に通学し、その後愛知県内の大学に合格もしたが、諸事情から同大学へは入学せず、平成25年4月28日に本邦を出国して中国に帰国し、その後韓国に留学するなどして、現在は中国人男性と結婚して中国に在住している。控訴人は、名古屋入管収容中、毎日、娘Dと電話で連絡を取り合い、現在も、電話やメールで娘Dと連絡を取り合っている。(乙12、13、19、35)
3 本件裁決の違法性について
(1) 控訴人の母が生存していれば中国残留邦人に該当する者であること
ア
前記認定によれば、控訴人母は、昭和62年10月の死亡時までに身元は判明しなかったものの、もともと日本国籍を有していた、いわゆる中国残留孤児であると認められるから(前記2(1)ア)、控訴人は、原則として、母を日本国民とする者として、国籍法附則5条1項による届出(同条3項による期間伸長あり)により日本国籍を取得し得る地位にあったといえるところである(前記2(1)エ)。なお、控訴人母は、中国において中国人男性(控訴人の父親)と婚姻しているが(前記2(2)ア)、そのことのみによって控訴人母が日本国籍を離脱したとは断定できないところであり、その他に控訴人母が日本国籍を離脱したと認めるべき証拠はない。そして、現に平成18年から平成26年までの9年間に、国内外で合計133名(うち109名が中国籍の者)が国籍法附則5条1項により日本国籍を取得しており(その多くは就籍による。前記2(1)エ)、その多くは中国残留孤児の子であろうと推測されるところである。もっとも、控訴人の場合は、平成21年11月の初来日以後相当期間を経ているから、届出期間の伸長を認める同条3項の規定によっても、その届出期限を徒過している可能性は高いといえるが、それは上記のような法的知識を有していなかったが故のことと考えられ、上記のとおり、控訴人がもともと日本国籍を取得し得る地位にあったことは、本件裁決に当たって特に重視して考慮されるべき事柄であったというべきである。
イ
また、いわゆる身元未判明孤児であっても、昭和60年当時の厚生省援護局長通知(援発第208号)により本邦への永住帰国援護の対象とされており、控訴人母もこれに該当する者であったといえるから、昭和62年頃、控訴人母本人が希望しさえすれば、同人及び控訴人(未成年で未婚の子は少なくともその対象となっており、前記2(2)アのとおり、当時の控訴人はこれに該当した。)は帰国旅費国庫負担の対象となり、永住帰国に関して日本国から各種の支援を受けられる立場にあったといえるところ(前記2(1)イ。なお、その後の立法により、中国残留邦人等への支援は法的に更に強化されているところである(前記2(1)ウ)。)、控訴人母は、前記認定のとおり、生前の昭和62年9月頃には、永住帰国を希望するに至っていたことが認められるから(前記2(1)イ)、同年10月に死亡してさえいなければ、控訴人もまた控訴人母とともに本邦に永住帰国していた可能性が高かったということができ、このような控訴人母や控訴人の立場にある者は、その後の法整備等により、日本国籍を離脱せずに維持していたかどうか等に応じて、入管法別表第二の「日本人の配偶者等(日本人の子として出生した者)」又は「定住者」として在留資格を付与されているところである(前記2(1)オ)。そして、平成27年9月30日までに、現に6700人以上(家族を含めて2万人以上)もの多数の中国残留邦人が現に本邦への永住帰国を果たしているものである(前記2(1)オ)。以上のとおりであるから、控訴人母が生存していれば、控訴人が中国残留邦人の子として、控訴人母とともに本邦に永住帰国して在留資格を付与されるべき立場にあったこともまた、本件裁決に当たって特に重視して考慮されるべき事柄であったというべきである。
ウ
なお、被控訴人は、本邦に永住帰国した中国残留邦人と同数弱程度の者らは本邦に一時帰国するに留まっており、中国残留邦人の全てが本邦に永住帰国をするわけではなく、控訴人母が当初は永住帰国する気はない等の回答をしていたことから、同人が永住帰国を希望していたとはいえない旨主張するが、中国残留邦人らは、望郷の念が益々高まる一方で、中国の養親らに対する恩義、中国で形成された親族関係、日本での受入親族らへの遠慮、日本での新たな生活への不安等々、様々な要因から永住帰国をするかどうかを容易には決めかねる状況にあったものと思料され、控訴人母もそのような様々な思いを経て、最終的には永住帰国の意思を固めていたと認められるところであるから、被控訴人の上記主張は認められない。また、被控訴人は、原審において、控訴人母が日本人であることを示す公的な書類は存在しないことなどに鑑みると、控訴人母が中国残留孤児である旨認定することは困難である上、仮に、控訴人母が中国残留孤児であったとしても、当該事情は在留特別許可の許否の判断において斟酌され得る一事情にすぎない旨主張し、当審においてもこれを維持している。しかし、当審における調査嘱託の結果によると、昭和59年の第1回訪中調査において、当時の厚生省が控訴人母を中国残留孤児と認定したことが認められ、上記主張の前段は明らかに誤っている。しかも、被控訴人は、本件裁決時はもとより当審に至っても上記調査嘱託の結果が判明するまでこのことを認識していないばかりか、これを調査しようとした形跡もうかがわれない。このことと上記主張の内容からすると、被控訴人は、要するに、本件裁決に当たり控訴人母が中国残留孤児に当たるか否かは裁決の結論に影響を及ぼすものではないと考えていたといわざるを得ないのであり、本件裁決に当たって十分に考慮すべき事情を全く考慮していないに等しい。
(2) 控訴人とAとの成熟かつ安定した実質的な夫婦関係
ア
控訴人とAは、前記認定(前記2(4)アないしウ)のとおり、平成23年末頃から交際を開始し、平成24年3月頃には肉体関係を持ち、控訴人と前夫Eとの婚姻関係が既に実質的に破綻していたといえる平成25年5月以降、実質的に内縁関係にあったといえる同居生活を送り、控訴人が同年8月▲日にEと協議離婚した後には、法律婚を意識して再婚禁止期間(待婚期間)の経過を心待ちにしていたといえるものであり、本件裁決のなされた平成26年1月27日には、その交際期間は約2年1か月、同居期間は約9か月であって、いずれも著しく長いとはいえないものの、双方の婚姻に対する考え方を確かめ合うには十分な期間を経過しており、その交際開始から内縁関係を経て婚姻関係に至る間の真摯さは、本件裁決前後に控訴人が名古屋入管に収容されていた期間中、Aが足繁く同入管に通い詰め、控訴人を精神的に励まし続け、その後も現在に至るまで仲睦まじく生活しており、両名とも当審において、今後も真摯に夫婦生活を継続していきたい旨供述していることからも明らかである。したがって、控訴人とAとの実質的夫婦関係は、本件裁決時において既に十分に安定かつ成熟しており、このことは本件裁決に当たり十分斟酌されるべき事柄であったということができる。他方、控訴人の実子である娘Dは、現在では中国で婚姻生活を送っていると認められるから(前記2(5))、中国に在住している同人との親子関係を特に考慮する必要はなく、たとえ遠く離れていても、控訴人及びAにおいて、電話やメール等の通信手段により娘Dとの良好な関係を築いていけば良いことであると思料される。
イ
被控訴人は、本件裁決時である平成26年1月27日の時点で、控訴人とAが未だ法律婚の関係になかったことを指摘するが、最高裁判所平成25年(オ)第1079号同27年12月16日大法廷判決において、民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は、平成20年当時において、憲法14条1項、24条2項に違反するに至っていた旨判示されているのであり、これに従えば、平成25年8月▲日に前夫Eとの離婚が成立している控訴人の再婚禁止期間が経過するのは同年11月▲日となり、同日には控訴人がAと婚姻することは可能であったものであり、それが本件裁決後の平成26年2月にまで遅れたのは、当時通用していた6か月間という不必要に長く違憲の再婚禁止期間の規定によって婚姻の届出が妨害されていたからであるにすぎないというべきであるから、本件裁決時に控訴人とAとの法律婚が未だ成立していなかったことを殊更問題視するのは相当でない。また、被控訴人は、控訴人は中国において約41年間生育し、本邦に入国するまで我が国と何ら関わりを有していなかった稼働能力のある成人女性であって、これに比して、本件裁決時点における控訴人の本邦在留期間は約4年2か月と短いものであることを指摘し、控訴人を中国に送還することに特段の支障があるとはいえない旨主張する。しかし、前記認定のとおり、控訴人の夫であるAが日本において仕事に就き、その給与収入により生計が成り立っていることからして(前記2(4)ウ)、上記のとおり真摯な夫婦関係にある控訴人とAが日本を離れて中国で暮らすことは事実上不可能というべきであって、控訴人の中国での生活期間と本邦での在留期間の長さを単純に比較して、控訴人が我が国で日本人男性と実質的な夫婦生活を営んできた重みを殊更軽視することは相当であるとはいえない。さらに、被控訴人は、控訴人が一時期化粧品のインターネットでの通信販売を行っていたことを問題視するかのようであり、控訴人とAが相互に相手の収入等を把握していなかったことをもって、両名の間に経済的扶助の事実はなかったことが明らかである旨主張するが、控訴人の供述によっても、上記インターネット通販による利益は月額4万円ないし8万円程度のものであり、控訴人はその後反省してインターネット取引をやめているのであって、お互いの収入状況を把握し合っていない時期があったからといって、実質的に真摯な夫婦関係を営んでいたことを否定し切れるものでもないから、被控訴人の上記主張は採用できない。加えて、被控訴人は、控訴人はEの配偶者として「日本人の配偶者等」の在留資格を有しながら、遅くとも控訴人が名古屋に転居した平成23年11月18日以降、「日本人の配偶者等」としての活動をしていなかったから、控訴人が入管法22条の4第1項7号により在留資格を取り消されるべき者であったことは明らかである旨主張するが、本件の事実関係に照らしても、控訴人が千葉県から名古屋市へ単身転居した後もマンションの賃料はEが負担していたのであり(前記2(3)イ)、別居の事実それ自体で控訴人が「日本人の配偶者等」としての活動をしていなかったとは断じ難いから、被控訴人の上記主張は採用できない。
(3) 控訴人の行っていた売春行為について
ア
他方、前記1に記載のとおり、控訴人は入管法24条4号ヌ(売春関係業務従事)の退去強制事由に該当する行為を行ったと認められるものであり、控訴人は、前記認定のとおり、売春勧誘行為により罰金1万円の刑に処せられ、また、本件証拠上、控訴人本人の供述しかないことは措くとしても、控訴人が売春行為により相当額の収入を得たことを自認していることは確かであって(前記2(3)ウ)、これらの事実が本件裁決に際して消極要素として考慮されるべきことは当然のことであるといえる。
イ
しかしながら、現行の売春防止法では、売春行為それ自体を犯罪としておらず、売春の勧誘行為等のほか、売春の斡旋や売春場所の提供等の周辺行為が刑事罰の対象とされているものであるところ、控訴人が売春防止法違反により受けた刑罰は、上記のとおり、1回の売春の勧誘行為による罰金1万円の刑のみであり、上記控訴人の供述によっても、自らが売春を行った期間は、他者に雇われて行っていたといえる期間が2か月程度、自ら行っていた期間が2か月程度のことであり、控訴人が他者を売春に巻き込んだり、他者を利用し搾取したりする行為は一切しておらず、いずれも組織的背景はないところであって、その動機も、別居した日本人夫から生活費の援助がない中で、中国から呼び寄せた実子を日本の学校に通わせようと焦って行ったというものであって、控訴人がその当時置かれた状況からすると酌むべき点があり、控訴人もこれらの行為を真摯に反省していると認められるところである。したがって、控訴人の上記売春行為を控訴人の悪性として殊更重視することは相当であるとはいえない。
(4)違法性の整理
以上(1)ないし(3)の認定説示によれば、本件裁決は、もともと控訴人母が日本人であって生存していれば中国残留邦人に当たる者であり、控訴人も日本国籍の取得、日本への永住帰国及び在留資格の付与がなされるべき立場にあったという特に重大な事項があるにもかかわらず、なすべき最低限の調査をも全く行わないまま、これを殊更無視又は軽視した上、控訴人とAとの間に成熟かつ安定した実質的な夫婦関係が形成されていたことや、控訴人を中国へ帰国させることによる控訴人やAの不利益を無視又は著しく軽視する一方で、当時日本人男性の妻であった控訴人が別居中の夫から十分な生活費の支援を受けられない中で、中国の実子を日本に留学させる費用を捻出するために心ならずも短期間行ったという動機に酌量の余地があり、かつ、それ自体同種事案の中で必ずしも重大とはいえない売春行為を重大視して、控訴人の悪性を著しく過大に評価することによってなされたものというべきであり、その判断の基礎となる事実に対する評価において明白に合理性を欠くことにより、その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことは明らかであるというべきであるから、裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法なものというほかはない。よって、控訴人による本件裁決の取消請求には理由がある。
4 本件処分の違法性について
本件処分は、名古屋入管局長から本件裁決をした旨の通知を受けた名古屋入管主任審査官が、入管法49条6項に基づいてしたものであるが、上記3において述べたとおり、本件裁決に裁量権の範囲を逸脱濫用した違法性があって取り消されるべきである以上、これを前提とする本件処分も違法というほかなく、その取消請求にも理由がある。
第4 結論
以上によれば、控訴人の本件各請求(控訴の一部取下げ後のもので、本件裁決及び本件処分に対する各取消請求)は、いずれも理由があるから認容すべきところ、これと結論の異なる原判決は失当であるから、その主文第2項の範囲で変更することとし、主文のとおり判決する。